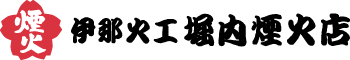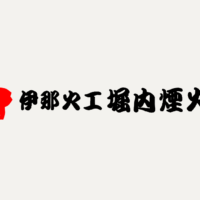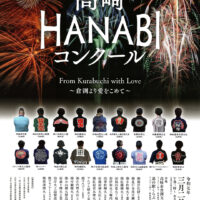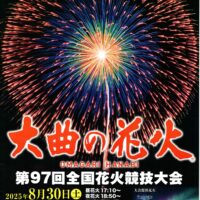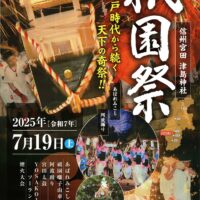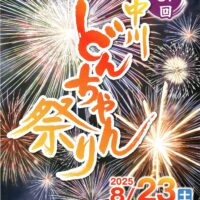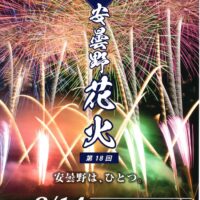花火と堀内煙火店の歴史

創業 明治三十二年十月二十四日
創業 明治三十二年十月二十四日
- 1543年
(天文12年) - 種子島に鉄砲伝来
- 1549年
(天文18年) - 火薬の原料である硝石の製法が伝わる
- 1560年
(永禄3年) - 吉田神社の祭で流星、 もしくは手筒のようなものが使用されたのではないかと言われる
- 1589年
(天正17年) - 伊達正宗が米沢城で花火を鑑賞
- 1612年
(慶長18年) - 徳川家康が駿府城で花火を鑑賞
- 1644年
(天保元年) - 隅田川で民間花火が上げられる
- 1648年
(慶安元年) - 江戸市中花火禁止令が出る
- 1751年
(宝暦元年) - 現在のように筒から打ち上げる形式が始まる
- 1877年
(明治10年) - 横浜で平山氏が洋火花火を打ち上げる
- 1899年
(明治32年) - 堀内煙火店創業
鉄砲火薬類取締法公布
軍用火薬等も不足し、 民間の火薬製造を許可することになる
この頃各地で煙火競技会が開催され、 型物花火が登場する - 1910年
(明治43年) - 鉄砲火薬類取締法改正 (営業許可制)
火薬類取扱免状制度が定められる
玩具花火の製造は都道府県知事の許可制に
この頃から芯物花火が人気を呼ぶようになる - 1917年
(大正6年) - 煙火は各府県の警察の管轄となる
- 1924年
(大正13年) - この頃、長野をはじめ各地で組合が結成される
- 1930年
(昭和5年) - 警視庁が塩と硫黄の配合を禁止
- 1933年
(昭和8年) - 東西「煙火工業組合」を結成
- 1945年
(昭和20年) - 9月26日、長野市平柴の諏訪神社祭礼で花火打ち上げを実施
10月、マッカーサー司令部が火薬製造を禁止 - 1946年
(昭和21年) - アメリカ軍の希望により日本各地で独立祭 (7月4日) の花火 打ち上げを実施
- 1948年
(昭和23年) - 8月、GHQより火薬製造の許可がおりる
黒色火薬を年間100tの範囲で製造 玩具花火はすすきなど6品目に限られる - 1998年
(平成10年) - 堀内煙火店、 長野冬季オリンピック閉会式にて打ち上げ
※参考資料/武藤輝彦著 「日本の花火のあゆみ」